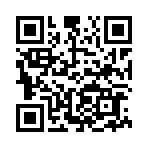2008年04月17日
視力3cm、東大
高校の先輩から、本をいただきました。
視力3cmという弱視の障害
(このいい方は、著者には、ふさわしくないですが……)
を持ちながら、福岡高校から東京大学に合格された「小川明浩」さんの本です。

その中の一部です。
「ハンデを設ければ大丈夫と思いこんで、障害者へのケアをそれっきり忘れてしまう…。
それはある意味で、どんな差別より酷なことではないでしょうか。
大事なのは、「自分を活かせる位置を見つけること」だと思います。
障害を一つの長所・短所ととらえて、それを活かせる、カバーできる関わり方を見つけていくことが、
必要なのではないでしょうか?」
お母さんの対応の仕方など、とても参考になりました。
ことあるごとに、人に勧めています。
視力3cmという弱視の障害
(このいい方は、著者には、ふさわしくないですが……)
を持ちながら、福岡高校から東京大学に合格された「小川明浩」さんの本です。

その中の一部です。
「ハンデを設ければ大丈夫と思いこんで、障害者へのケアをそれっきり忘れてしまう…。
それはある意味で、どんな差別より酷なことではないでしょうか。
大事なのは、「自分を活かせる位置を見つけること」だと思います。
障害を一つの長所・短所ととらえて、それを活かせる、カバーできる関わり方を見つけていくことが、
必要なのではないでしょうか?」
お母さんの対応の仕方など、とても参考になりました。
ことあるごとに、人に勧めています。
2008年03月25日
予備校の選び方
知人より、予備校の相談を受ける機会が増えてきました。
相談で多いのは、
大手予備校のS予備校、K塾、地元のK予備校です。
実は、期間の大小は、ありますが、上記の3校とも、以前数学の講師をしていました。
結論からいうと、「本人のやる気次第で、どの予備校も変わらない。」と話します。
志望大学によって、多少の違いは、ありますが、予備校の言っていることは、あまり真に受けず、
経験者などの話などを、参考にするとよいと思います。
いずれにしても、基本の繰り返しが、大事だと思います。自分で、復習の流れを、いかにして、
作るかだと思います。
相談で多いのは、
大手予備校のS予備校、K塾、地元のK予備校です。
実は、期間の大小は、ありますが、上記の3校とも、以前数学の講師をしていました。
結論からいうと、「本人のやる気次第で、どの予備校も変わらない。」と話します。
志望大学によって、多少の違いは、ありますが、予備校の言っていることは、あまり真に受けず、
経験者などの話などを、参考にするとよいと思います。
いずれにしても、基本の繰り返しが、大事だと思います。自分で、復習の流れを、いかにして、
作るかだと思います。
2008年03月11日
一橋大、佐賀大医学部に合格しました。
今回の受験で、一番【主体的学習システム】を、させた生徒2名が、無事合格しました。
特に、一橋大に、合格した生徒は、最初数学が、いやでいやで、「人に説明する」なんて、とんでもないと、いやがっていたのを、強制的に、【主体的学習システム】をさせました。
同じ問題を、複数人に説明させると、徐々に理解が、深まっていったようです。
「人に説明する」前に、私にリハーサルすると、効果的であると、気づかせてくれたのも、この生徒です。
いろいろな意味で、エポックメイキングになった二人です。
特に、一橋大に、合格した生徒は、最初数学が、いやでいやで、「人に説明する」なんて、とんでもないと、いやがっていたのを、強制的に、【主体的学習システム】をさせました。
同じ問題を、複数人に説明させると、徐々に理解が、深まっていったようです。
「人に説明する」前に、私にリハーサルすると、効果的であると、気づかせてくれたのも、この生徒です。
いろいろな意味で、エポックメイキングになった二人です。
2008年02月29日
九大、東大、京大の入試問題(数学)
今年の、数学の入試問題(前期)について、雑感を書きます。
九大(理系) 簡単になっている。毎年出ていた数Cの範囲はなく、数Ⅲの問題も、手をつけやすかった。
九大(文系) とっつきにくい問題が多かった。計算量も、増えた。
東大(理系) やや難化。1番で、1次変換(新課程で、復活)が出た。
東大(文系) 例年通り
京大(理系) 例年通り
京大(文系) 例年通り。2番の、図形は、京大らしくないやさしい問題。
九大の文系、東大の理系を除いて、解き易くなっています。
特に、九大の理系は、難しい問題ばかりをやってきた生徒は、拍子ぬけしたと思います。
基本問題の繰り返しが大事であるという、思いを強くしました。
九大(理系) 簡単になっている。毎年出ていた数Cの範囲はなく、数Ⅲの問題も、手をつけやすかった。
九大(文系) とっつきにくい問題が多かった。計算量も、増えた。
東大(理系) やや難化。1番で、1次変換(新課程で、復活)が出た。
東大(文系) 例年通り
京大(理系) 例年通り
京大(文系) 例年通り。2番の、図形は、京大らしくないやさしい問題。
九大の文系、東大の理系を除いて、解き易くなっています。
特に、九大の理系は、難しい問題ばかりをやってきた生徒は、拍子ぬけしたと思います。
基本問題の繰り返しが大事であるという、思いを強くしました。
2008年02月24日
受験生が家庭教師(7)
天神2丁目(福岡銀行横)に、レンタル自習室があり、自習と【主体的学習システム】が、できます。
駿台、河合塾などの予備校の授業の後や、空き時間に利用できます。
授業の内容の復習などに、【主体的学習システム】をすると、より効果的です。
「駿台の授業内容」を河合塾の生徒に、「河合塾の授業内容」を駿台の生徒に、説明させたりしています。
もちろん、私もお相手(説明をする役と説明を聞く役の両方担当)します。
中学生、高校生、宅浪生、中学受験の方なども、ぜひご検討下さい。
駿台、河合塾などの予備校の授業の後や、空き時間に利用できます。
授業の内容の復習などに、【主体的学習システム】をすると、より効果的です。
「駿台の授業内容」を河合塾の生徒に、「河合塾の授業内容」を駿台の生徒に、説明させたりしています。
もちろん、私もお相手(説明をする役と説明を聞く役の両方担当)します。
中学生、高校生、宅浪生、中学受験の方なども、ぜひご検討下さい。
2008年02月12日
受験生が家庭教師?(6)
大学受験のこの時期に、生徒から、こんな相談をよく受けます。
「今、何をやったらいいのか、わかりません。」
この時期は、今までやった基本の復習だと思います(予備校では、直前対策と称して、なぜか難問をさせます)。
できれば、受験生でも、【主体的学習システム】をすれば、いやおうなしに、基本の確認をすることになります。
家庭教師のような形を何人かに、作っておければ、と思います。
自分の周りの、弟、妹、近所の高校生、高校の後輩などとの関係を、作っておきましょう。
お母さんやお父さんを、生徒役にするのも、とてもよいです。
「今、何をやったらいいのか、わかりません。」
この時期は、今までやった基本の復習だと思います(予備校では、直前対策と称して、なぜか難問をさせます)。
できれば、受験生でも、【主体的学習システム】をすれば、いやおうなしに、基本の確認をすることになります。
家庭教師のような形を何人かに、作っておければ、と思います。
自分の周りの、弟、妹、近所の高校生、高校の後輩などとの関係を、作っておきましょう。
お母さんやお父さんを、生徒役にするのも、とてもよいです。
2008年02月11日
受験生が家庭教師?(5)
予備校の講師室のよくある風景
生徒A「先生、この問題のここがわかりません。」
講師「そうか、そこが、わからないのか!そこは、……(中略)……。
どうだ。わかったか!」
生徒A「(なんとなく)わかった気がします。」
講師「そうか。それは、よかったな。」
この光景を見て、このとき、頭がよくなったのは、講師の方で、生徒の方ではないといつも思っています。
よくわかっている生徒は、生徒に、説明させます。もしくは、自分が話したことを、繰り返させます。
受験生に、家庭教師をさせると、このような受け身の流れは、減っていきます。
生徒A「先生、この問題のここがわかりません。」
講師「そうか、そこが、わからないのか!そこは、……(中略)……。
どうだ。わかったか!」
生徒A「(なんとなく)わかった気がします。」
講師「そうか。それは、よかったな。」
この光景を見て、このとき、頭がよくなったのは、講師の方で、生徒の方ではないといつも思っています。
よくわかっている生徒は、生徒に、説明させます。もしくは、自分が話したことを、繰り返させます。
受験生に、家庭教師をさせると、このような受け身の流れは、減っていきます。
2008年02月11日
受験生が家庭教師?(4)
「受験生が、説明役に回ると、学力アップにつながる」
ということは、次のことからも、わかります。
高校、中学、予備校などのクラスの状態です。
①1学期の始めのクラスの状態
生徒A、生徒B、生徒C、生徒D、同じ状態で、ほぼ同じレベル。
②1学期の終わりのクラスの状態
生徒Aが、よい成績を取り出していることが、みんなにわかり、生徒Bが、授業の内容が、わからないので、生徒Aに質問をし始める。生徒Aが、答えているのを、みんなで見ている。
③2学期の終わりの状況
生徒Aに、生徒B、生徒C、生徒Dが質問をして、生徒Aが、3人に答える。
すなわち、生徒Aは先生の代役をしていることになる。
④受験時
生徒Aは、合格の力がついており、生徒B、C、Dは、普通の状態。
自然と、「説明をする役」と「説明を受ける役」に分かれており、「説明する役」は、その場は、大変ですが、結果として、得をしているはずです。
ということは、次のことからも、わかります。
高校、中学、予備校などのクラスの状態です。
①1学期の始めのクラスの状態
生徒A、生徒B、生徒C、生徒D、同じ状態で、ほぼ同じレベル。
②1学期の終わりのクラスの状態
生徒Aが、よい成績を取り出していることが、みんなにわかり、生徒Bが、授業の内容が、わからないので、生徒Aに質問をし始める。生徒Aが、答えているのを、みんなで見ている。
③2学期の終わりの状況
生徒Aに、生徒B、生徒C、生徒Dが質問をして、生徒Aが、3人に答える。
すなわち、生徒Aは先生の代役をしていることになる。
④受験時
生徒Aは、合格の力がついており、生徒B、C、Dは、普通の状態。
自然と、「説明をする役」と「説明を受ける役」に分かれており、「説明する役」は、その場は、大変ですが、結果として、得をしているはずです。
2008年02月10日
受験生が家庭教師?(3)
前回の記事の「予備校生」→「高3生」の続きです。
今日は、上記の高3生の自宅で、「高3生」→「高2生」の【主体的学習システム】があります。
実は、二人の、ご家庭が、昔からの知り合い(十数年前に沖縄でいっしょだったそうです)で、実現しました。
こういう組み合わせは、なかなかないです。
マッチングが、なかなか難しいです。
作っては、続かず、作っては、続かず、作っては、ようやく続いている、という感じです。
今日は、上記の高3生の自宅で、「高3生」→「高2生」の【主体的学習システム】があります。
実は、二人の、ご家庭が、昔からの知り合い(十数年前に沖縄でいっしょだったそうです)で、実現しました。
こういう組み合わせは、なかなかないです。
マッチングが、なかなか難しいです。
作っては、続かず、作っては、続かず、作っては、ようやく続いている、という感じです。
2008年02月09日
受験生が家庭教師?(2)
実は、すでに、1件始めています。
私の作成プリントを「予備校生→高3生」の【主体的学習システム】を、昨年の10月くらいから、始めました。
喫茶店などで、していたのですが、周りの雑音などが、多くあまりいい環境とはいえません。
そこで、高3生の自宅に、予備校生に、行ってもらい、【主体的学習システム】をしてもらいました。
お互いに、ゆっくりできて、楽しかったそうです。
私の作成プリントを「予備校生→高3生」の【主体的学習システム】を、昨年の10月くらいから、始めました。
喫茶店などで、していたのですが、周りの雑音などが、多くあまりいい環境とはいえません。
そこで、高3生の自宅に、予備校生に、行ってもらい、【主体的学習システム】をしてもらいました。
お互いに、ゆっくりできて、楽しかったそうです。
2008年02月07日
受験生が家庭教師?
タイトルにも、ありますが、受験生同士で、【主体的学習システム】(説明のし合い)をさせると、次第に、説明を聞く役が不足してきます。説明する側の成績が伸びることが、わかってくるからです。
そこで、浪人生に、家庭教師をさせることを、考えています。もちろん、私のフォロー付きです。
料金は、交通費と、私の諸経費のみで、格安になるはずです。
これにより、浪人生にとっては、成績アップ、ご家庭にとっては、格安で、家庭教師が受けられるという両得になる気がします。
幸いなことに、大名に場所も、借りることができているので、そこでの指導も可能です。
さっそく、内容を詰めていきたいと思います。
そこで、浪人生に、家庭教師をさせることを、考えています。もちろん、私のフォロー付きです。
料金は、交通費と、私の諸経費のみで、格安になるはずです。
これにより、浪人生にとっては、成績アップ、ご家庭にとっては、格安で、家庭教師が受けられるという両得になる気がします。
幸いなことに、大名に場所も、借りることができているので、そこでの指導も可能です。
さっそく、内容を詰めていきたいと思います。
2008年02月01日
2008年01月30日
赤坂の近くに、場所が、借りれそうです。
今まで、ベローチェやドトールコーヒーなどの、喫茶店で、【主体的学習システム】を、していました。
場所が、借りれることになりそうです。地下鉄の赤坂駅の近くです。
ただし、場所の借り賃が、発生しそうなので、料金体系を作らなくてはいけません。
結構、大変です。
場所が、借りれることになりそうです。地下鉄の赤坂駅の近くです。
ただし、場所の借り賃が、発生しそうなので、料金体系を作らなくてはいけません。
結構、大変です。
2008年01月14日
センター試験直前対策
センター試験直前対策授業が、どの予備校でもあっていますが、効果は、どうでしょうか?
一体、新しいことを習って、いつ復習するのでしょうか?
基本的なことの確認をさせてくれればいいのですが、担当した経験では、難しめの設定になっていることが、多いです。
あのイチローでさえも、試合の直前は、基本動作の確認に集中すると、聞いたことがあります。
センターの直前は、今までの基本問題の復習に徹するべきだと思います。
一体、新しいことを習って、いつ復習するのでしょうか?
基本的なことの確認をさせてくれればいいのですが、担当した経験では、難しめの設定になっていることが、多いです。
あのイチローでさえも、試合の直前は、基本動作の確認に集中すると、聞いたことがあります。
センターの直前は、今までの基本問題の復習に徹するべきだと思います。
2008年01月14日
「相手に気づいてもらう」ことは、難しいです。
センター試験まで、1週間を切りました。
受験生同士で、【主体的学習システム】をさせていますが、気になることがあります。
少し目を離すと、説明する側が、解答を見せながら、説明しています。
これをしてしまうと、両方とも、わかった気になってしまいます。
どこがわかって、どこが分からないかを、順序よく、進めていくことが大切です。
相手に気づいてもらように、時間をかけると、お互いに伸びるはずです。
時間がかかって、面倒なので、したくないようです。
この辺の、手間ひまを、避ける傾向にあるようです。
受験生同士で、【主体的学習システム】をさせていますが、気になることがあります。
少し目を離すと、説明する側が、解答を見せながら、説明しています。
これをしてしまうと、両方とも、わかった気になってしまいます。
どこがわかって、どこが分からないかを、順序よく、進めていくことが大切です。
相手に気づいてもらように、時間をかけると、お互いに伸びるはずです。
時間がかかって、面倒なので、したくないようです。
この辺の、手間ひまを、避ける傾向にあるようです。
2008年01月14日
昨日のわくわく授業
「話し合いで読み解こう」~福田美佐子先生の国語~
番組HPより
聞く力・話す力を学校全体で育てている熊本県宇城市立松橋(まつばせ)小学校。
6年2組の担任、福田美佐子先生の国語の授業では、
子どもたち自身がみんなで話し合いながら、文章の内容を深く読み取ります。
http://www.nhk.or.jp/wakuwaku/jugyo/080113.html
「二人対話」と「全体対話」があり、聞くだけの理解と、説明する理解の違いで、【主体的学習システム】に、つながります。
この番組は、参考になります。再放送は、金曜日の深夜です。
番組HPより
聞く力・話す力を学校全体で育てている熊本県宇城市立松橋(まつばせ)小学校。
6年2組の担任、福田美佐子先生の国語の授業では、
子どもたち自身がみんなで話し合いながら、文章の内容を深く読み取ります。
http://www.nhk.or.jp/wakuwaku/jugyo/080113.html
「二人対話」と「全体対話」があり、聞くだけの理解と、説明する理解の違いで、【主体的学習システム】に、つながります。
この番組は、参考になります。再放送は、金曜日の深夜です。
2008年01月05日
さいころの問題
問1 「3回(3個の)さいころを投げて、2回同じ目と3回とも違う目が出る確率を求めよ。」
問2 「4回(4個の)さいころを投げて、3種類の目と2種類の目が出る確率を求めよ。」
問1と問2は、同じ様な問題に見えますが、難度がかなり違います。
問1は、なんとなく解けますが、問2は、自分が出した数字を、きちんと説明できないと、正解になりにくいです。
【主体的学習システム】(人に説明するシステム)を、この問題でさせると、理解度や、問題に対して、真剣に考えているかどうかが、よくわかります。
また、人に説明すると、その人が自分と違う考え方で、解いてきた場合、とても勉強になります。
特に、数学が苦手な生徒の突拍子もない質問が、勉強になります。
問2 「4回(4個の)さいころを投げて、3種類の目と2種類の目が出る確率を求めよ。」
問1と問2は、同じ様な問題に見えますが、難度がかなり違います。
問1は、なんとなく解けますが、問2は、自分が出した数字を、きちんと説明できないと、正解になりにくいです。
【主体的学習システム】(人に説明するシステム)を、この問題でさせると、理解度や、問題に対して、真剣に考えているかどうかが、よくわかります。
また、人に説明すると、その人が自分と違う考え方で、解いてきた場合、とても勉強になります。
特に、数学が苦手な生徒の突拍子もない質問が、勉強になります。
2007年12月26日
確率の【主体的学習システム】
昨日、確率を、私の説明が終わっている生徒に、別の生徒に対して、説明させました。
「さいころを、3回投げて、積が2の倍数、3の倍数、5の倍数、4の倍数、6の倍数、9の倍数、10の倍数になる確率を求めよ(2通り)。」
という問題なのですが、解けるだけでは、だめで、全体の説明(まとめ)が、大事です。
案の定、説明役の生徒は、私と2回していたのですが、理解が不十分でした。
「さいころを、3回投げる」問題は、奥が深いのですが、既存の参考書では、2、3問簡単に載っているだけです。
入試では、最頻出(昨年のセンター試験にも出ました)なので、早目に整理しておく必要があります。
受験生でなくても、ぜひ挑戦してみませんか?
頭の体操になりますよ(笑)。

「さいころを、3回投げて、積が2の倍数、3の倍数、5の倍数、4の倍数、6の倍数、9の倍数、10の倍数になる確率を求めよ(2通り)。」
という問題なのですが、解けるだけでは、だめで、全体の説明(まとめ)が、大事です。
案の定、説明役の生徒は、私と2回していたのですが、理解が不十分でした。

「さいころを、3回投げる」問題は、奥が深いのですが、既存の参考書では、2、3問簡単に載っているだけです。
入試では、最頻出(昨年のセンター試験にも出ました)なので、早目に整理しておく必要があります。
受験生でなくても、ぜひ挑戦してみませんか?
頭の体操になりますよ(笑)。

2007年12月19日
「軌跡の解法」の【主体的学習システム】
昨日、大学受験生4人で、【主体的学習システム】を、しました。
【主体的学習システム】とは、「私」→「生徒A」→「生徒B」と伝言ゲームのように、受験問題の解法や、チェック方法などの説明をしていく勉強方法です。
数Ⅱの「軌跡の解法」が、テーマです。
4人とも、大手予備校で、4月から授業を受けているはずなのですが、説明ができません。
「軌跡の解法」は、
「求める文字を(x、y)とおいて、目標は(x、y)の式で、いらない文字を消去することがある」
が、基本です。
これなどを、使いながら、教科書レベルの基本問題から、国公立の2次レベルの問題まで、説明させたのですが、あまりできません。
入試では、解けるだけではなく、複数の解法の比較で、「なぜその解法なのか?」という整理が大事になってきます。
予備校の授業を聞いただけでは、この点が、身につかないというのが、現状のようです。
【主体的学習システム】とは、「私」→「生徒A」→「生徒B」と伝言ゲームのように、受験問題の解法や、チェック方法などの説明をしていく勉強方法です。
数Ⅱの「軌跡の解法」が、テーマです。
4人とも、大手予備校で、4月から授業を受けているはずなのですが、説明ができません。
「軌跡の解法」は、
「求める文字を(x、y)とおいて、目標は(x、y)の式で、いらない文字を消去することがある」
が、基本です。
これなどを、使いながら、教科書レベルの基本問題から、国公立の2次レベルの問題まで、説明させたのですが、あまりできません。
入試では、解けるだけではなく、複数の解法の比較で、「なぜその解法なのか?」という整理が大事になってきます。
予備校の授業を聞いただけでは、この点が、身につかないというのが、現状のようです。