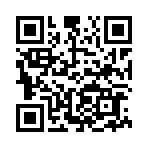2007年12月19日
「軌跡の解法」の【主体的学習システム】
昨日、大学受験生4人で、【主体的学習システム】を、しました。
【主体的学習システム】とは、「私」→「生徒A」→「生徒B」と伝言ゲームのように、受験問題の解法や、チェック方法などの説明をしていく勉強方法です。
数Ⅱの「軌跡の解法」が、テーマです。
4人とも、大手予備校で、4月から授業を受けているはずなのですが、説明ができません。
「軌跡の解法」は、
「求める文字を(x、y)とおいて、目標は(x、y)の式で、いらない文字を消去することがある」
が、基本です。
これなどを、使いながら、教科書レベルの基本問題から、国公立の2次レベルの問題まで、説明させたのですが、あまりできません。
入試では、解けるだけではなく、複数の解法の比較で、「なぜその解法なのか?」という整理が大事になってきます。
予備校の授業を聞いただけでは、この点が、身につかないというのが、現状のようです。
【主体的学習システム】とは、「私」→「生徒A」→「生徒B」と伝言ゲームのように、受験問題の解法や、チェック方法などの説明をしていく勉強方法です。
数Ⅱの「軌跡の解法」が、テーマです。
4人とも、大手予備校で、4月から授業を受けているはずなのですが、説明ができません。
「軌跡の解法」は、
「求める文字を(x、y)とおいて、目標は(x、y)の式で、いらない文字を消去することがある」
が、基本です。
これなどを、使いながら、教科書レベルの基本問題から、国公立の2次レベルの問題まで、説明させたのですが、あまりできません。
入試では、解けるだけではなく、複数の解法の比較で、「なぜその解法なのか?」という整理が大事になってきます。
予備校の授業を聞いただけでは、この点が、身につかないというのが、現状のようです。